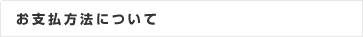|
精油とハーブのプロフィール事典《杜仲 Guttapercha tree》
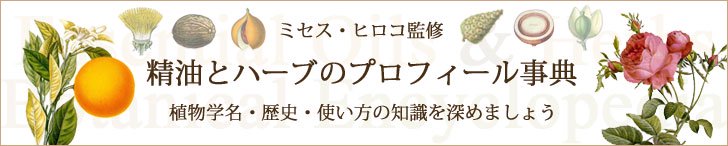
英名:Guttapercha tree  トチュウ植物画:plantillustrations.org トチュウ植物画:plantillustrations.org
トチュウは、中国中央部を原産とするトチュウ科の落葉高木です。「杜仲」の名前は、この植物の薬効によって悟りを開いた仙人の名前が由来であるとされています。非常に起源の古い植物で、6千年前から植生し、氷河期を生き抜いた「生きた化石植物」と呼ばれています。中央ヨーロッパ、北アメリカ、日本などでこの植物の化石が発見されています。日本には奈良時代に渡来し、何度かのブームを経て、90年代に健康茶として広く知られるようになりました。樹高は15〜20mに成長し、雌雄異株で楕円形の葉をつけ、4月頃に緑色がかかった白色の小さな花を多数咲かせます。樹皮は生薬に、葉は杜仲茶として利用され、生薬名は「杜仲」(とちゅう)で、強壮、鎮痛、強精、降圧などの作用があり、腰痛や肩こり、精力の減退、高血圧などに用いられてきました。属名の「Eucommia」はギリシャ語で「良いゴム」を意味し、樹皮、枝、葉を傷つけると「グッタペルカ」と呼ばれる粘り気のある白い液体が滲出し、固まった樹脂は天然ゴムとして利用されています。その他に家畜や養魚の飼料に葉を混ぜて与えると脂肪分の少ない肉になるため、畜産などでも利用されています。ティーの味はくせがなく、ほのかな甘みがあって飲みやすく、禁忌がなく、安全性の高い健康茶です。中国最古の本草書「神農本草経」では「上品」(じょうほん=無毒で日常的に使用できる植物)に分類されています。中国で使用されてきたのは樹皮ですが、日本では葉が主に利用され、葉に含まれるゲニポシド酸やアスペルロシドの成分には内臓脂肪の蓄積抑制や血圧降下の働きがあるためメタボリックシンドローム対策や血圧調整に良いとされています。
ハーブの使用部位:(生薬)樹皮、(茶)葉 ハーブの成分:(樹皮)樹脂、リグナン、イリドイド(葉)杜仲葉配糖体(ゲニポシド酸、アスペルロシド) 一般的なハーブに期待される作用:強壮、鎮痛、強精、血圧降下、抗肥満 ハーブティーブレンド:ルイボス、バードックルート、ウーロン茶 ハーブティーの抽出時間:5分〜10分 ハーブティーの味:ほのかな甘み
◆血糖値調整、ダイエット、健康増進に
◆アロマテラピーとハーブの資格取得に関してはこちらのページをご覧ください。
|
||||||||||||||||||||||
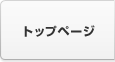 |
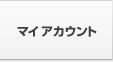 |
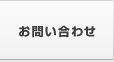 |
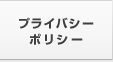 |
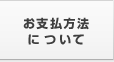 |
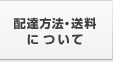 |
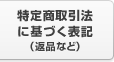 |
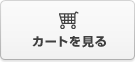 |
|
2012-2025 Copyright (C) Holistic Aroma Academy, all rights reserved.
|



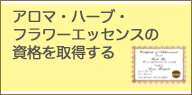
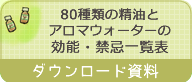
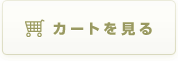


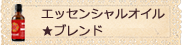
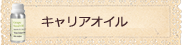
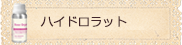
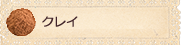
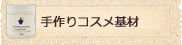
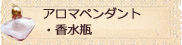
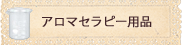
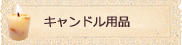
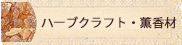
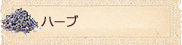
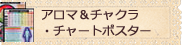
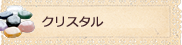
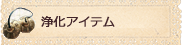
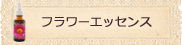
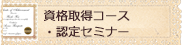
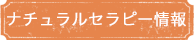


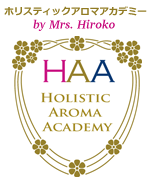
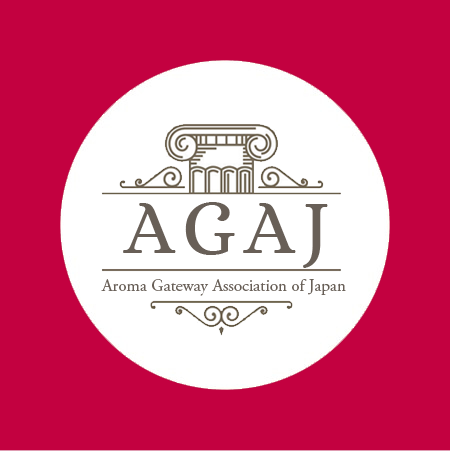



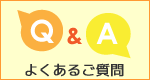

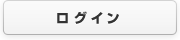



 《トチュウ》ドライハーブのプロフィール
《トチュウ》ドライハーブのプロフィール