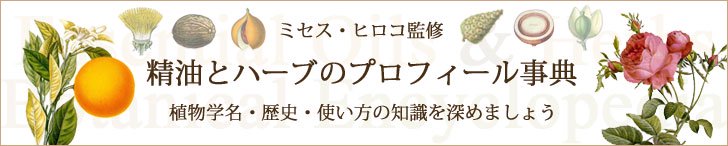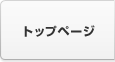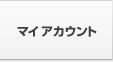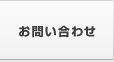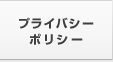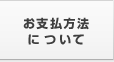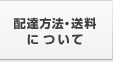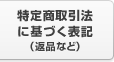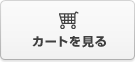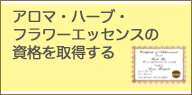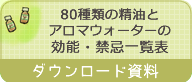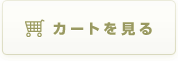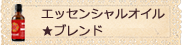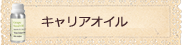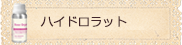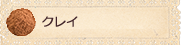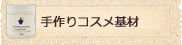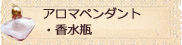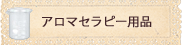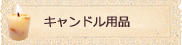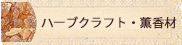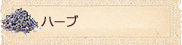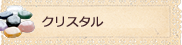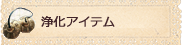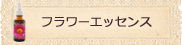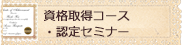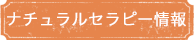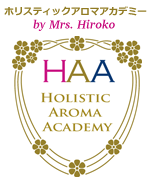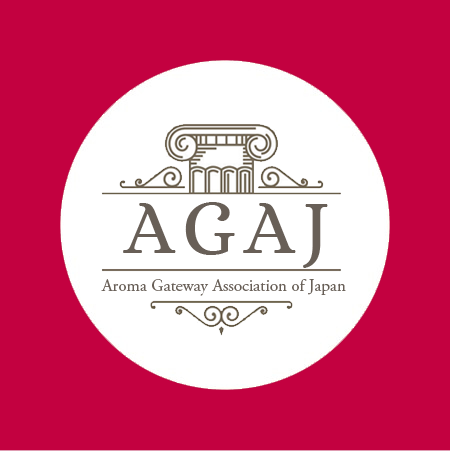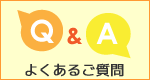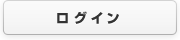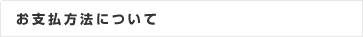英名:Cotton plant
学名:Gossypium(ゴシピウム)
和名:ワタ(綿)
科名:アオイ科
種類:多年草、一年草
草丈:約60〜120cm
原産地:中南米、インド
 ワタ(綿)植物画:Wikipedia
ワタ(綿)植物画:Wikipedia
ワタ(綿)は、エチオピア南部、メキシコを原産とするアオイ科ワタ属の多年草(もしくは一年草)で、木綿の原料となる綿花のとれる工芸作物です。草丈は60〜120 cmに成長し、高温、多雨の場所を好み、掌状の葉を付けます。7月〜8月頃にハイビスカスの花に似た白、黄白、黄、紅、青、緑、茶などの色の花を咲かせます。花は一日しか咲かず、9月〜11月になると結んだ実が弾けて、割れたところから白色のふわふわした「綿花」(めんか、コットンボール)が見られます。綿花は花ではなく種子を包んでいる「綿毛」で摘み取られて繊維に加工されると木綿布(コットン生地)になります。綿栽培の歴史は古く、メキシコでは8000年前の種子が発見されています。その他にもエジプト、インド、ペルーなどでも古くから綿が栽培されていました。現在では、中国、アメリカ、メキシコ、ブラジル、インド、エジプト、パキスタンなどの世界各地で栽培され、栽培種によって採れる繊維の長さが異なります。日本には8世紀に初めて渡来したとされ、その後15世紀になって国内での栽培が広がりました。木綿が一般的になったのは江戸時代で、それまでは麻布が衣類に使われていました。木綿は染色しやすく、吸湿性、保温性に優れるので布団綿にも利用されてきました。現在、日本での栽培は減少し、木綿はほぼ海外からの輸入品です。綿の種子からは綿実油(めんじつゆ)が取れ、食用油として利用されています。精製された綿実油は淡黄色の半乾性油で低温になると白く濁ります。リノール酸50〜60%、オレイン酸20〜30%、パルミチン酸20〜25%、その他ステアリン酸、ミリスチン酸、アラキドン酸などで構成され、加熱しても酸化しにくく、揚げ物などにも適しています。綿実油の外用塗布はされないためアロマセラピーやハーブ浸出油の基材および化粧品原料などには利用されません。
《ワタ(綿)》ドライハーブのプロフィール
ハーブの使用部位:綿花(布地)種子(綿実油)
ハーブの成分:(綿花)セルロース(綿実油)リノール酸50〜60%、オレイン酸20〜30%、パルミチン酸20〜25%、ステアリン酸、ミリスチン酸、アラキドン酸など
《ワタ(綿)》ドライハーブの使い方
◆クリスマスの飾りに
綿花を雪に見立ててクリスマスツリーやリースの飾りにします。
◆ドライフラワー、ブーケに
綿花を枝付きのまま飾ります。
◆糸つむぎ体験に
綿花を少しずつねじりながら糸状にして、台紙に巻き付けます。

アロマとハーブの資格を取得する
◆アロマテラピーとハーブの資格取得に関してはこちらのページをご覧ください。