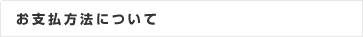|
精油とハーブのプロフィール事典《ギシギシ Japanese dock》
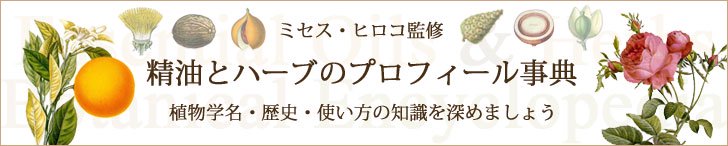
英名:Japanese dock  ギシギシ植物画:イラストAC ギシギシ植物画:イラストAC
ギシギシは、日本、朝鮮半島、中国、台湾、ロシア原産のタデ科の多年草です。古くはこの植物の名前を「之」(し)と呼び、その根を薬用したことから「之の根」(しのね)と呼ばれてきました。その他にも別名をウマスカンポ、ウマスイバ、ウシグサ、ウシノシタ、オカジュンサイなどともと呼ばれ、道端などに見られる食用出来る野草として知られています。ヨーロッパ大陸原産の「イエロードック」(ナガバギシギシ)は近縁種です。ギシギシの名前の由来には茎を擦り合わせたり、穂を揺らすとギシギシ音を立てるからなどの説があります。1mにも成長する大型の植物で茎は直立し、葉は長楕円形、夏に茎先に淡緑色の小さな花を多数咲かせます。早春にとれる若芽から薄皮を取り除いてゆでたものは山菜や野草として食用され、特有のぬめりがあることから「オカジュンサイ」と呼ばれ、お浸しや酢の物などに利用されてきました。若芽にはシュウ酸が含まれているため多量摂取は避けます。ハーブとしての有用部は黄色い根と根茎で生薬名を「羊蹄、羊蹄根」(ようてい、ようていこん)と言い、「羊蹄」は、花の形が羊の蹄に似ていることに因んでいます。緩下、収れん、消炎、抗菌などの作用があり、便秘や皮膚疾患、水虫などに用いられてきました。その他にも根は褐色の染料として用いられてきましたが、現在では繁殖力の旺盛さから雑草の扱いとなっています。
ハーブの使用部位:根、根茎 ハーブの成分:アントラキノン、アントロン、タンニン 一般的なハーブに期待される作用:緩下、抗菌、収れん、消炎 ハーブティーの味:苦みと酸味
◆便秘に ◆水虫、おでき、腫れ物に
◆アロマテラピーとハーブの資格取得に関してはこちらのページをご覧ください。
|
||||||||||||||||||||||
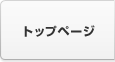 |
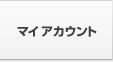 |
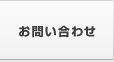 |
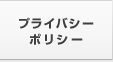 |
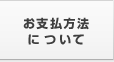 |
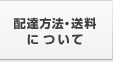 |
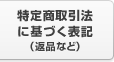 |
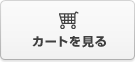 |
|
2012-2026 Copyright (C) Holistic Aroma Academy, all rights reserved.
|



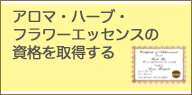
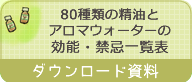
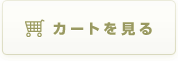


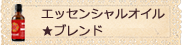
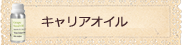
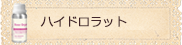
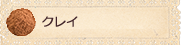
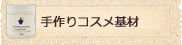
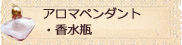
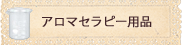
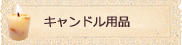
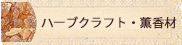
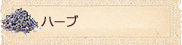
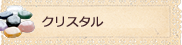
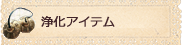
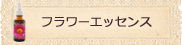
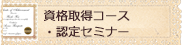
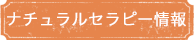


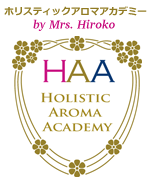
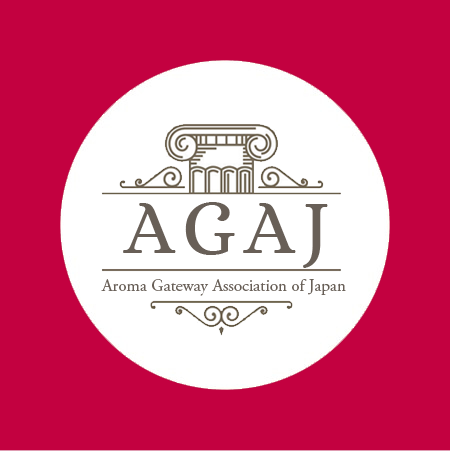



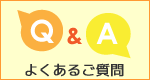

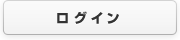



 《ギシギシ》ドライハーブのプロフィール
《ギシギシ》ドライハーブのプロフィール