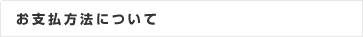英名:Japanese star anise
学名:Illicium anisatum(イリシウム・アニサツム)
和名:シキミ(樒)
科名:マツブサ科
種類:小高木
樹高:2〜5m
原産地:本州〜沖縄諸島、済州島
 シキミ植物画:Wikipedia
シキミ植物画:Wikipedia
シキミは、本州〜沖縄諸島、済州島に自生するマツブサ科シキミ属の常緑小高木です。属名の「Illicium」は「(芳香で)誘惑する」、種小名の「anisatum」は「(セリ科の)アニス様の香り」をそれぞれ意味しています。和名の「シキミ」は、この植物が四季を通して美しいため「四季美」、あるいは果実が有毒のため「悪しき実」、小花が密集する様子から「重実」(しきみ)となったなどの説があります。日本では仏事に用いられ、寺院や墓地に植えられてきた馴染み深い植物です。そのため、仏事に因んだ別名が多く、コウノハナ、コウハナ、コウノナ、シキビ、ハナノキ、ハナシバ、ハカバナ、ブツゼンソウ、コウシバ、マッコウノキなどとも呼ばれています。古くは神事にも用いられ、「サカキ」(榊)の名前で呼ばれていた時代もありました。樹皮は灰色で葉は枝先に集まり、3月〜5月にかけて枝先に黄白色の小花を多く咲かせます。花後に生る星形で緑色の果実は熟すと黒褐色となり、袋果が割れると茶色の種子が弾け出ます。植物の全草(葉、茎、根、花、果実、種子など)に神経毒性成分のアニサチンやネオアニサチンが含まれ、特に果実と種子は毒性が強く、誤食は嘔吐、腹痛、下痢、痙攣、意識障害などを起こして死に至る可能性があります。国内でのシキミの果実は植物としては唯一「毒物及び劇物取締法」によって劇物指定されています。誤食の原因の一つにはシキミの果実が中華料理の香辛料に使われる「八角」(スターアニス、トウシキミ、大茴香、学名:Illicium verum、この種にはシキミのような毒性はない)と似ているためで、見分けとしてはシキミの果実はスターアニスに比べると小さく、八つの角の先端が丸くならずに尖っているのが特徴です。(※スターアニス植物は国内に植生していない)シキミ植物の毒性はかつての日本の土葬時代に墓の周りに植えることで野犬や鼠などから墓を守り、強い芳香が邪気祓いになると考えられてきました。生の葉や樹皮には精油が含まれ、ツンとする特徴的な芳香があります。芳香成分は主に1,8-シネオール 、サフロール、リナロール、ミリスチシンなどで乾燥葉や樹皮を粉にしたものは「抹香」(まっこう、粉末の香)として仏事に利用されてきました。抹香はシキミの樹皮と葉の乾燥粉末ですが、丁子、白檀、沈香、安息香、甘松香、竜脳などの香材とブレンドした粉末香もあります。抹香はその他にも「香盤時計」と呼ばれる香炉に利用されてきました。香盤時計は、お香の燃焼時間が一定であることから燃焼時間によって時刻を計る道具で香時計、時香盤(じこうばん)、常香盤(じょうこうばん)とも呼ばれています。古代インドから中国を経て日本に伝来し、主に寺院などで用いられてきました。香盤時計は灰のうえに専用の木枠を用いて敷いた抹香の一端に点火し、燃焼時間によって時間の経過を計ります。抹香はご焼香にも使われ、焼香では手で摘んだ抹香を香炉にくべて焚きます。抹香の香煙は故人(仏)を弔い、焼香者との間を結ぶ架け橋となり、仏の喜ぶ「食べ物」になると考えられています。
※シキミは誤食すると有毒ですが、シキミから作られた「抹香」の香煙には毒性はありません。
 《抹香》インセンスのプロフィール
《抹香》インセンスのプロフィール
インセンスの使用部位:葉、樹皮
一般的なインセンスに期待される作用:邪気祓い
インセンスとしての香りのイメージ:ツンとするスパイシーな香り
 《抹香》インセンスの使い方
《抹香》インセンスの使い方
◆香盤時計に
香盤炉に専用の木枠を用いて抹香を敷き、一端に点火します。
◆手作りインセンスに
他の香材と合わせて、お香の材料に加えます。

アロマとハーブの資格を取得する
◆アロマテラピーとハーブの資格取得に関してはこちらのページをご覧ください。
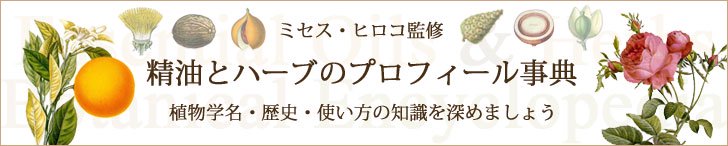
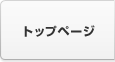
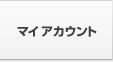
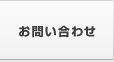
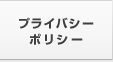
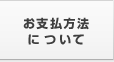
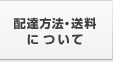
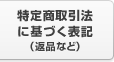
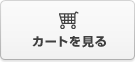



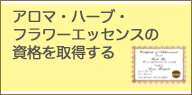
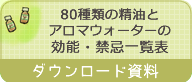
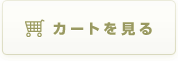


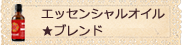
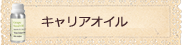
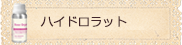
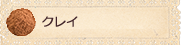
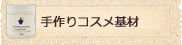
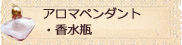
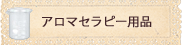
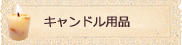
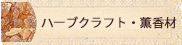
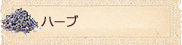
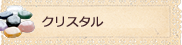
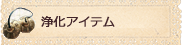
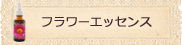
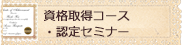
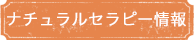


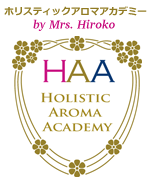
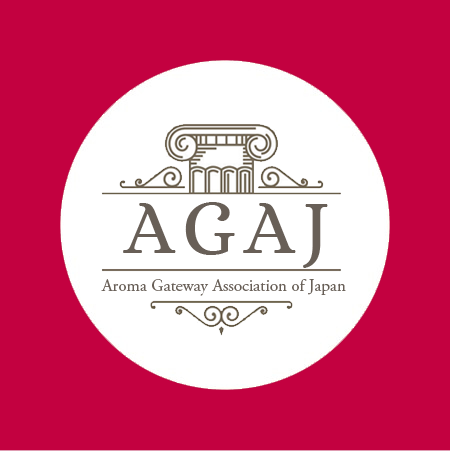



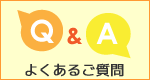

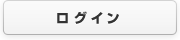




 《抹香》インセンスのプロフィール
《抹香》インセンスのプロフィール